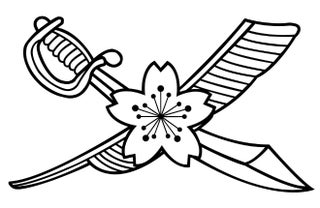命がけで翻訳された「赤毛のアン」 ~幸せの灯火~
はじめに
皆さんは「赤毛のアン」というお話をご存知でしょうか。カナダのL.M.モンゴメリ原作のこの物語が、翻訳者である祖母の村岡花子によって日本ではじめて紹介されたのは第二次世界大戦直後 のことでした。
この4月から放映中のNHK連続テレビ小説「花子とアン」の原案となった「アンのゆりかご 村岡花子の生涯」で、祖母 の人生を孫の私が書くにいたったのには色々な理由があります。
私は幼いときから祖母と「赤毛のアン」のことを母から聞いて育ちました。「カナダ人の友人から託された原書を、第二次世界大戦中に命がけで訳したもの」だと。戦時下では英語は敵国語。なぜ祖母は危険を冒してまでその本を訳すことにこだわったのだろう。空襲警報の最中、原書と翻訳原稿を持って逃げた覚悟とは何だったのか。英語が好きでカナダ人との友情があったというだけでなく、もっと深い動機がなければできないことではないか。 私の中でさまざまな問いがめばえ始めました。
村岡花子の生きた時代、日本には子ども向けの良書が少なく、教育をうける機会も不平等、婦人参政権もありませんでした。資料がぎっしりつまった祖母の書斎で過去を手繰り寄せる作業を進めるうちに、高度経済成長期に生まれた私には想像もできない「当然の権利がない世界」を目の当たりにし、改めて衝撃が走りました。本がなく学校にも行けない子どもたちがあふれ、女性にとっても生きるのが困難な社会の中で、花子はいかに生きたのでしょうか。そして、もし今生きていたとしたら、子どもたちに何を伝えようとしたのでしょうか。
村岡花子の生い立ち
村岡花子は10歳のとき、給費生として父親の多大な期待を背負い、カナダ人宣教師が教鞭をとる東洋英和女学校に入学しました。当時は、限られた特権階級の人しか高等教育を受けられなかったので、花子は入学後、二つのカルチャーショックを受けることになります。一つは、西洋文化・英語との出会いであり、もう一つは自分とは別世界の上流階級出身の同級生との出会いでした。
規律正しい寮生活は英語で行われ、「神様のもとでは全てが平等である」という精神のもと、当時の社会常識とは別世界の寄宿生活を通じて、花子は次第に向学心をのばしていきました。
また一方で、一見華やかに見える華族や富裕層の華やかな女性たちでさえ、必ずしも幸せでないという事実にも直面しました。花子をとり巻く実家の庶民の生活と、裕福な学友たちの境遇の両方を見ていたことで、花子のリベラルな精神が築かれていきました。
もともと大の本好きの花子は、東洋英和の図書室にある英語の原書を夢中になって読みふけり、15、6歳のころには学内で「英語の花ちゃん」と言われるほど、英語が得意になっていたようです。
日本文学との出会い
英米文学のとりことなった16歳の花子は、大正天皇の従姉妹でありのちに歌人となる柳原白蓮(びゃくれん)女史に出会い、その後の人生に大きな影響を受けます。年上の学友である白蓮女史は日本の古典文学全般に精通しており、源氏物語などを詳しく花子に説いてくれたそうです。英語と英米文学ばかりを勉強していた花子は日本の文学についての知識は浅かったため、自らの教養の欠陥に気づき、自国の文学も学ぶことを決意します。
その後、歌人佐佐木信綱先生の門下生となり、短歌を学ぶようになります。五・七・五の形式美と、言葉を厳選しながら表現すること、日本の言葉の周りに漂っている感情や色を感じ取ることを身に付けていきました。そして佐佐木先生が薦めた森鴎外翻訳のアンデルセン作「即興詩人」を読み、その日本語のあまりの美しさに、翻訳文学のあり方について深く真髄に触れることとなります。
花子は多感で瑞々しい感覚を持つ十代のときに、西洋文学と日本文学の両方に出会い、外国人教員や年齢を超えた友人との語らいの中で、英語と日本語の言葉に肌で触れ、その感覚を全身で習得していきました。
激動の時代、花子の覚悟とは
当時は、富国強兵・帝国主義が叫ばれ、実に戦争の多い時代でした。花子の幼少期から結婚前までの間に、日清・日露・第一次世界大戦が、結婚後には日中戦争・第二次世界大戦が勃発し、関東大震災の被害にも遭います。時代の流れとは裏腹に、花子は カナダ人、イギリス人、アメリカ人の先生や友人たちと出会い、その個人的な交流がかけがえのないものになっていきます。
翻訳の仕事を始め社交的で前向きな花子でしたが、愛児(長男・道雄)を6歳という幼さで亡くすという、絶望の淵に立たされます。悲嘆にくれて一度はペンを折りそうになった花子、その後自らを奮い立たせ、「日本中の子どもたちのために」とマーク・トウェイン著の「王子と乞食」の翻訳を成し遂げます。
花子はどんな書物でも訳すのではなく、子どもや女性のための読み物を訳すことにこだわり続けました。大きな悲しみを経て、花子の母性が翻訳家としてのゆるぎない覚悟へと確立していったのです。
迷いがなくなった花子は不屈の魂のもと、子どもたちの幸せの灯火になるようにと「赤毛のアン」だけでなく「フランダースの犬」「ハックルベリィ・フィンの冒険」「クリスマスカロル」など、今ではすっかりお馴染みとなった英米文学を精力的に訳し、日本の子どもたちに紹介していきます。「どんな時代や境遇においても、優しさと笑いを持って生きて欲しい」「信じる力を持って生き抜けば、きっと幸せになれる」という花子の熱い思いが伝わるような文学を、繰り返し翻訳し、出版していきました。
戦後、花子はヘレン・ケラー女史来日の際に通訳を務めたことがありました。「日本には私以上に不幸な人たちがいるのに、なぜその人たちにもっと温かい手を差し伸べてくださらないのでしょうか」※という女史の言葉を、花子は後に日本ユネスコ協会連盟の副会長や各省庁の審議委員などを歴任した際に、さまざまな機会で伝え続けました。子どもたちへの愛情、人間への愛情こそがまさに花子の原動力だったのです。
※「村岡花子と赤毛のアンの世界」より
周りの女性に支えられて
花子の生きた時代には翻訳業という業種は一般的ではなく、女性が家庭を築きながら同時に能力を生かして仕事をするモデルケースが少なかったようにも見られます。花子は家庭と仕事の両立をめざした女性の先駆けではありますが、花子自身は特別な意識をもたず自然体でいたのではいかと思います。なぜなら、社会に出て自分を表現しなくても、豊かな教養と 経験を子育てと家庭に反映する、お手本にすべき女性たちと沢山出会っていたからです。花子はそんな女性たちの生き方から自身の立ち位置を悟り、家庭の主婦として、また翻訳家としての生き方を確立していきました。出版社を営む夫とともに創刊した「家庭」という機関誌では、「私はささやかなこの『家庭』に陣営を構えて、『生活派』の文学を提唱する」と述べています。バランスの取れた賢明な女性たちから刺激を受けたことで、不屈の精神を持ち続けながらどんな状況下でも翻訳をし続けることができたのではないかと思います。
難しいことを難しい言葉でいうのではなく、万人に分かり易い言葉で語ることも大切にしていたと言います。
シンガポールの皆さんへ
「子どもを本好きにする秘訣を教えてください」と聞かれたら、「小さい子で本が嫌いな子はいませんよ」と私は答えます。お母さんが日常的に絵本の読み聞かせをしてあげたら、その幼い子どもはきっと本が大好きになるでしょう。親御さんの声を通して物語が子どもに語られる時間は、子どもにとって甘美で優しくかけがえのないひと時なのです。そしてそのあたたかい記憶は、成長して本の世界以外に興味が増えても 心にしっかり刻まれていることでしょう。
「赤毛のアン」の主人公アンは、とても個性的で、色々なハプニングを起こし周囲を戸惑わせます。しかしそんなアンも、次第にバランスのよい素敵な女性に成長していきます。アンがそうであったように、幼児期の突飛と思われる個性はいつしかその角が丸くなり、常識を備えた大人へと成長していくものです。ですから、子ども時代はどうかその尖っている個性をきらめかせていただきたいと思います。
花子は大戦中のつらい時期、アンの言葉に幾度となく励まされました。戦時下でも、原書を守り敵国の言葉を翻訳し続けた理由とは、自分を支えてくれたその言葉を、日本の子どもたちに命がけで伝えたかったからではないかと思います。
「いま曲がり角にきたのよ。曲がり角をまがったさきになにがあるのかは、わからないの。でも、きっといちばんよいものにちがいないと思うの。」※この言葉は、時代を越えて私たちにもまっすぐに響く言葉ではないでしょうか。
※「赤毛のアン」L. M. モンゴメリ作 村岡花子訳
※2014年4月25日現在の情報です。最新情報は各機関に直接ご確認ください。









.jpg?optimize&width=320)