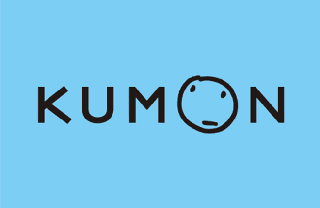人生は「自分で決める」~自調自考の大切さ~
グローバル教育への変遷
戦後の日本が国際化に向けて動き出したのは1980年代、ちょうど経済復興の波にのり、経済的に力をつけた時期でした。それはまさに、日本人がこれから海外で活躍する場がどんどん広がるであろうと予測された時代でもありました。1979年にはハーバード大学教授だったエズラ・ヴォーゲル氏が「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を著し、高度成長期の日本の勢いを世界に発信し衝撃を与えました。80年代に入ると「プラザ合意」があり、円高が急激に進行しました。いよいよ日本が世界経済の一員として活躍する時代がきたことを、誰もが実感したのです。
この時期は、日本の「教育」について考え直す時でもありました。明治維新以降、近代化を目指して先進国に追いつけ追い越せという心意気で進められてきましたが、21世紀に向けて、ヨーロッパやアメリカを理想とする教育に終止符を打つべき時が来たのです。同時に、新たな時代に即した教育に必要なことは何か、という議論が活発になりました。まさに日本にとって、「グローバル教育」への幕開けでした。
アジア初の高等学校を設立
日本が世界に目を向け始めたことで海外への渡航も急激に増加し、日本人のための学校も世界各地に設立され始めました。80年代の終わり頃、海外に20校近くある高等学校の全てはヨーロッパやアメリカでした。そこで、アジアで初の邦人向け高等教育機関として、海外生からのニーズをくみとり、91年に渋谷幕張シンガポール校を開校しました。
シンガポールに開校した理由は、まず言語が英語であったことと、東南アジア各地からの利便性の良さや医療の質の高さも魅力だったからです。2002年からは、日本の高等教育機関の中で東南アジアの研究にいち早く取り組んでいた早稲田大学と共同出資する形で、現在の早稲田渋谷シンガポール校になりました。
その頃、経済分野でも日本はアジアで非常に貢献していたので、経済開発のリーダーたる日本人に、将来のアジアの発展のためにしっかり学んでもらいたい、という熱い思いがありました。シンガポールで学ぶ意義の大きさは、過去も現在も、そしてこれからも変わることはないでしょう。
求められる「自調自考」の取り組み
渋谷教育学園の両校(渋谷校・幕張校)の教育目標に「自調自考」があります。ますます複雑化する社会を生き抜くために必要な主体的な行動の原動力であり、複雑化した課題を解決する力を養うための教育方針です。
この力は、グローバル時代に生きる子どもたちにとって更に求められるものだと感じます。グローバル社会では、次に何が起きるかわかりません。つまり生徒一人ひとりが考えて主体的に生きていくことが非常に大切で、自分で切り拓いていく積極性が強く求められるのです。
生きるために必要な資質で最も基本的なものに「自分で決める」ということが挙げられます。残念ながら、これは周囲と同意を得てものごとを進めることを良しとする日本ではなかなか育ちにくく、弱い部分でもあります。なぜ「自分で決める」ことが大切かと言えば、自分で決めることによって「自己肯定感」や自分で責任を取る覚悟を感じることができるからです。
内閣府による若者の意識調査では、日本人は世界的に比較すると「自己肯定感」が低く、自分に対する信頼が薄いという結果が出ています。それは「自分で決める」という行為が十分に行われていないからに他なりません。子どもは、自分の人生に必要なことを高等教育機関で身につけます。つまり思春期の6年間で、自ら調べ・学ぶ習慣を身につけることにより、その後の人生の確たる基盤ができるのです。その基盤ができていないと大学に行っても何をしたら良いのかわからなくなり、五月病になったり何も身につかないで終わってしまうことになりかねません。人生で最も多感な時期にこの力を養い日々実践することは、将来に向けて大きな糧になると確信します。
日本の教育の課題
日本は自国に特化した教育を100年ぐらい続けてきました。その特化した教育は日本語という言葉のバリアで守られ、外部からの影響をほとんど受けずに独自に進化したのです。つまり教育の「ガラパゴス化」が起こりました。その結果得られたものもあれば失ったものもあるのです。
「教育」は「文化」と深く関わりを持っています。日本は農耕民族の文化ですから皆が同じことをするのを好む文化です。そのため、日本の教育は皆に同じような力をつける「教育」として発達してきました。しかし、皆が一緒にやるという点では長けていますが、その反面、とがった才能を伸ばすという点においては、むしろマイナスになり、平均的な力だけを持つ面白味がない人間を育てることになります。もし、とがった教育を良しとすれば、その人の個性や強みを尊重し過ぎるあまり、バランスを欠いてしまう危険性もあります。学力で言えばまだらな学力が身についてしまうことになるのです。
成長の過程では、長所が欠点になり欠点が長所になることは多々あります。どちらを求めるかは難しいですが、「出る杭は打たれる」に象徴されるように、奇異の目にさらされたり大勢に潰されたりせずに、秀でた才能を周囲がいかに認め自らも伸ばしていくかが、今後の重要課題ではないでしょうか。
高等教育における改善すべき点としては、例えばタコツボ化してしまった日本の研究現場があげられるでしょう。アメリカの大学で実際現場を見ればわかりますが、日本の大学の先生方の研究室は全部個室なのに対し、アメリカの研究室は開放的で、密室にこもることができないようにできています。コーヒーを飲みながら、違う分野の先生方といろいろな話し合いがしやすいような仕組みになっているのです。日本では研究者があまり連携せず、自分のところにこもって研究をする、いわば個人が独自に発達してきたように思います。連携しないがゆえに失ったものが大きくなりました。ノーベル賞の受賞でも、近頃は個人だけの功績でなく、集団で研究した成果が実を結んで受賞に至っているケースが多いのは、連携の大切さを語る良い例と言えましょう。日本の大学は研究の現場でも、外国の研究者に対して開かれていないことが、グローバルな飛躍を妨げる大きな障壁になっているように感じます。これらの点が改善されない限り、今後世界で互角に戦うには厳しいと感じます。
子育てに大切なこと~ご家庭へのメッセージ~
お子さんの教育を考える時、一番大切なことは「自立心」と「好奇心」を育むことだと考えます。実際、好奇心旺盛で、何事にもやる気になって取り組む力が強い方が、幸福な人生を送れるものです。大学入試でも、求められる必要な力とは ①学力(10~20%)②論理的思考力(10~20%)③意欲・好奇心(60~70%)だと言われます。つまり、大半を占める「意欲・好奇心」は中等教育の6年間に身につけるべきなのです。
では「やる気」はどこから生まれるのでしょうか。答えは簡単で、それは「人間関係」から生まれるのです。周囲でいくら「やる気を出しなさい」と言っても無理な話で、お子さんが自分の「人間関係」の中から自然に育む以外に周囲が教えることは不可能です。人との繋がりが人間にやる気を促すことは確かですので、子育てでは、ぜひ良い「人間関係」の構築を大切にしていただきたいと思います。
良い「人間関係」の構築には、友だちと読書が大きく影響します。多感な思春期は、外の世界との関わりで子どもが大きく変わっていく時期でもあります。外の世界の中で一番影響のある存在は「友だち」で、自我を確立する段階での「友だち」から受ける影響は非常に大きいのです。親として、お子さんがどういう友だちを持っているかを知ることはとても大切です。ぜひお子さんの交友関係を把握するよう努めてください。子どもの友だちを知らずに子育てをしているとしたら、それはペットを飼っているのと同じことになってしまいます。
読書の大切さは言うまでもありません。「読書尚友」という言葉があるように、読書は優れた友を持つのと同様に重要です。読書を通して昔の賢人を友とし、そこから知恵を身につけることで良い人間関係を広げることができるでしょう。子どもを読書好きにするためには、まずは読み聞かせることが大切です。親が何もしないで本を読むように促しても、そうなるはずがありません。ご家庭では、ぜひ読書の重要性を再認識していただき、お子さんが出来るだけ多くの本に触れる機会をつくっていただくことを願っています。
※2016年1月25日現在の情報です。最新情報は各機関に直接ご確認ください。